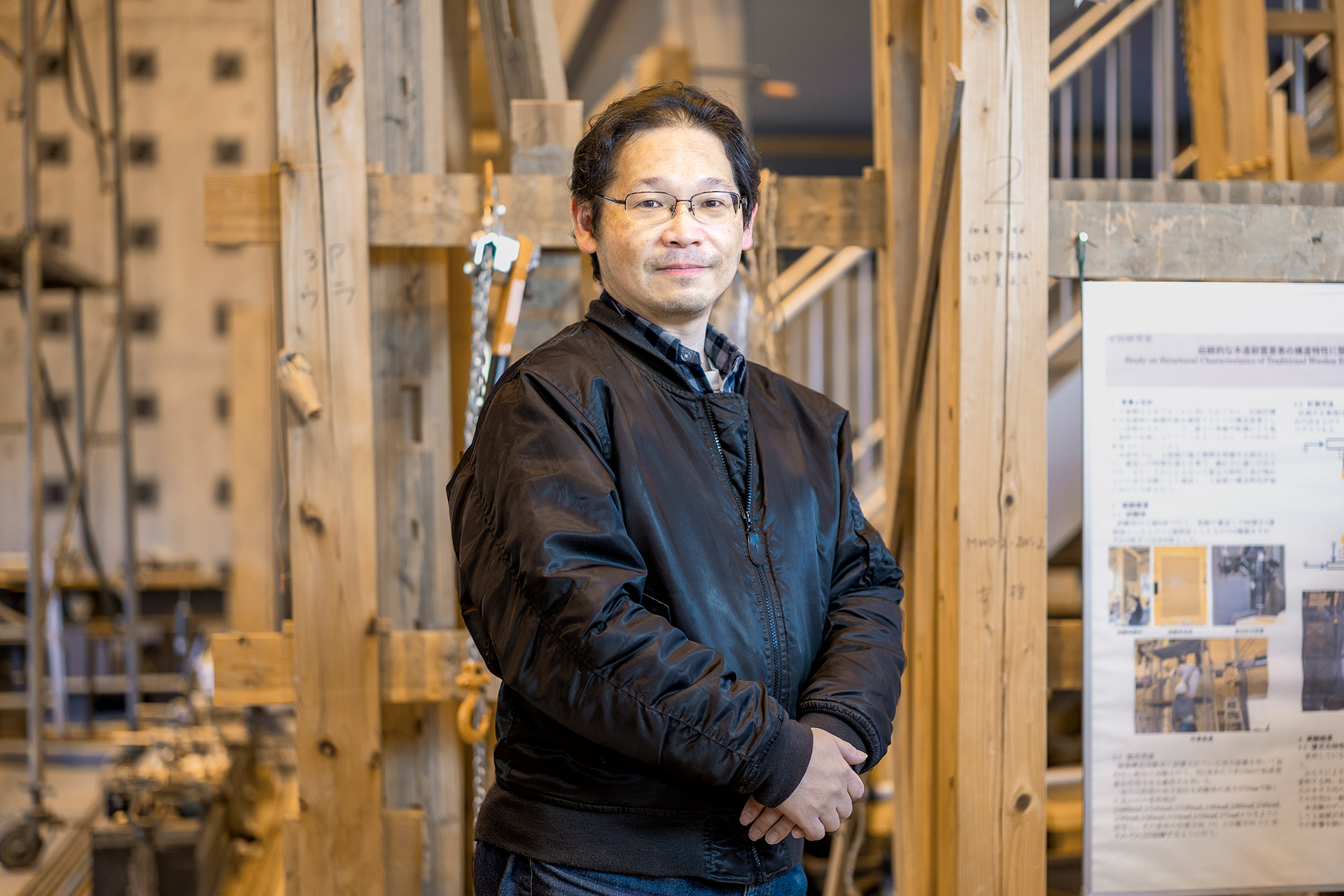ホーム ▶ 研究室紹介(環境学部) ▶ 中治 弘行 教授
災害時の「完全な倒壊」を防ぐ
ヒントを模索
伝統的な構法で作られた木造建築物の耐震強度について研究しています。1995年に発生した阪神・淡路大震災では多数の建築物が倒壊しましたが、その5年後に起こった鳥取県西部地震では、同時期に建てられた多くの建物が倒壊を免れていました(日野町)。大地震が起こった時、建物の一部が崩れたとしても、「完全な倒壊」を避けることができれば命が助かる可能性があります。土塗り壁などの仕様は地域によっても異なります。未だ不明な部分が多い伝統的構法には、未知の可能性があります。

大きな力に抵抗しつつ
ほどよく変形する機能
当研究室では、柱と梁で骨組みを作る「木造軸組」や「土塗り壁」などを含む構造物を、専門業者に依頼して実寸大で制作します。そして、できあがった構造物に徐々に負荷をかけ、どの部分から壊れるのか、どのように壊れるのかなどを記録します。データを分析する時は、構造物の強度だけでなく「可変性」にも注目。地震で負荷がかかった時にほどよく変形してエネルギーを消費することができ、且つ大きな力に耐えうる構造のヒントを模索しています。


あらゆることを学び、
試行する謙虚さを持とう
木造建築に関わる伝統的な構法は、文化的価値が非常に高いものです。しかし、こういった技術を用いて大規模な木造建築物を作ることは、現状では許可されていません。解明されていない部分が多くあるため、現代の耐震強度基準上では比較的低い評価を受けています。当研究の成果を伝統的構法による木造建築物の耐震性能評価へつなげることを目指し、作っては壊しの試行錯誤を、気づけば25年程続けています。これから入学する皆さんにも、試行や学習内容に「これはやらなくていい」と線引きをすることなく、積極的な姿勢で研究に臨んでほしいです。