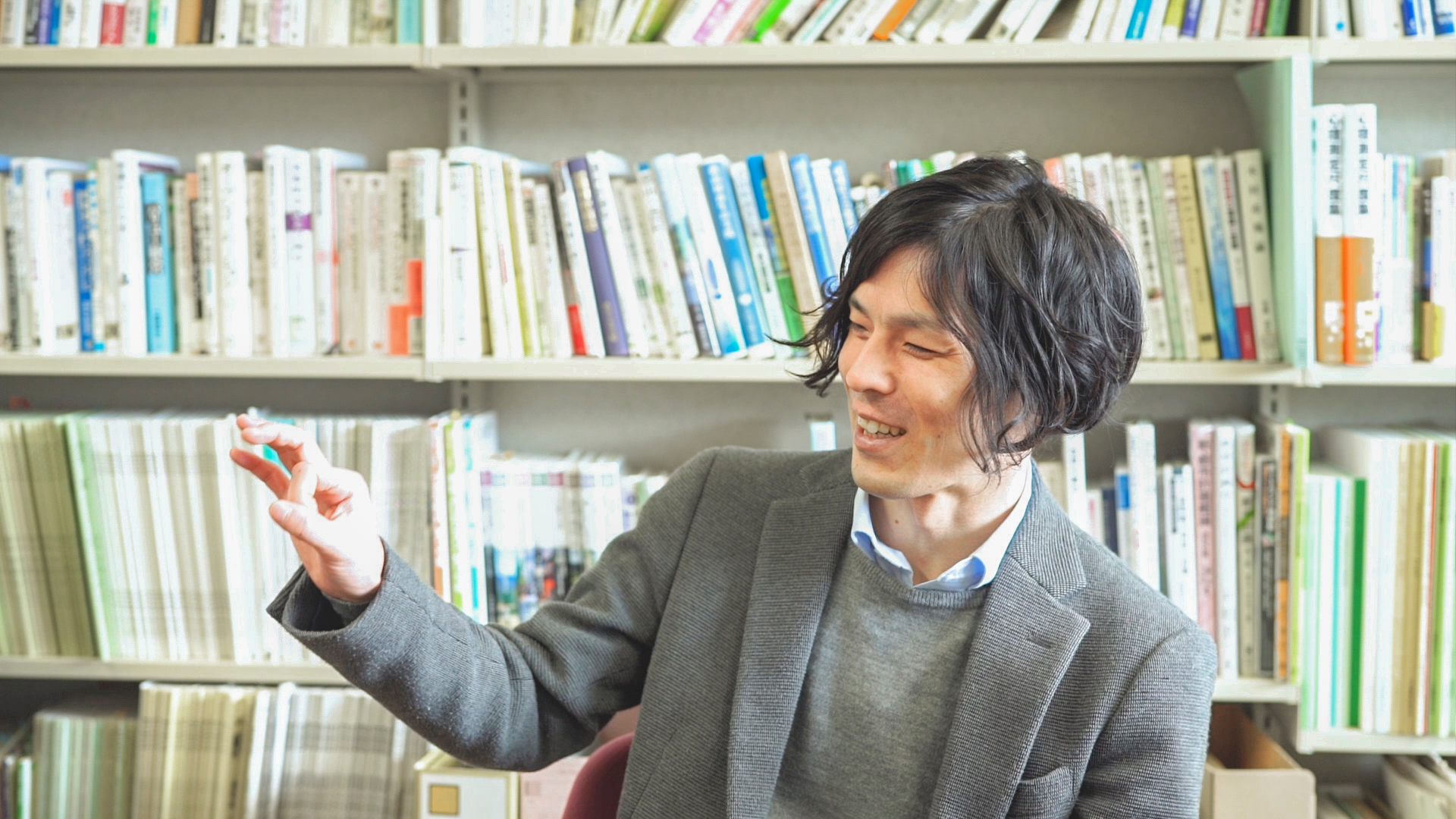ホーム ▶ 研究室紹介(環境学部) ▶ 山口 創 准教授
農村に存在するナレッジの継承など
地域の課題解決について考える
農村には、作物が不作の年でも収穫量を確保する栽培ノウハウや気候を読む知識など、言語化が難しい知識(ナレッジ)が数多く存在しています。こうした知識の多くは重要性が高いにもかかわらず、次世代へ継承できていないことが課題となっています。インタビューやアンケートなど基礎的な調査を行い考察していきますが、聞いた内容のどこに「ナレッジ」が存在するのか、判断することは簡単ではありません。こうした調査を通して、課題の本質をとらえる力、問題を解決するために道筋をつけていく力を身に付けられるよう指導していきます。

様々な課題への取り組みが
周辺の山村の課題解決につながる
農村には他にも交通空白地の拡大という課題もあります。高齢化が進む農村地域では、病院への行き来や買い物にバスが主要な移動手段となっていますが、財政負担が非常に大きく、路線の廃止が検討されています。しかし、廃止後は地域の人の移動手段がなくなり、生活そのものを維持できなくなります。研究室では、廃止後の新しい交通システムをどうしたらいいか、通院や買い物、習い事など生活をどの範囲まで支えるべきかということについて研究しています。鳥取における課題は多岐にわたりますが、こうした課題に取り組んでいくことが、今後周辺の山村の課題解決の一助になると考えています。

積極的に自らが動かなければ
成長にはつながらない
研究室では、学生たちに自分でテーマを考えるよう指導しています。それは、誰もまだ研究したことのない内容を研究したり、同じ分野でも視点を変えたりすることで、学生自身の視野を広げ、発想の訓練になるからです。学生たちはスポーツ、しゃんしゃん祭り(鳥取市で8月に行われる祭り)、学校教育、それと地域を結び付けたテーマに取り組んでいます。テーマはそれぞれ異なりますがゼミ生同士の議論は活発に行われています。もちろん壁に突き当たることもありますが、そんなときは周りの人に意見を求めることが大切です。本学は、先生やゼミ生だけではなく、地域の人々との交流もしやすく、学びのために最適な環境といえます。困難を乗り越え、できることが増えていくことこそ、成長の証だと思います。